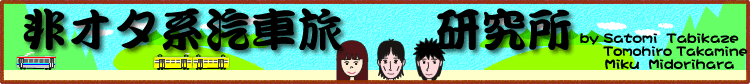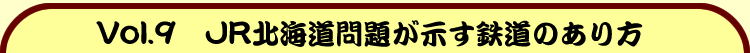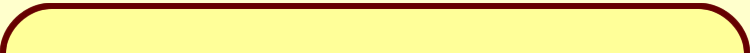=ローカル線の廃線=
土砂災害により廃線〜岩泉線
岩泉町内で起きた土砂災害で、岩泉線が不通となり、その後廃止された。
土砂災害により廃線〜高千穂鉄道
台風による洪水・土砂災害により不通になった高千穂鉄道が復旧を断念し、廃線。
津波被害によりBRTに〜気仙沼線
東日本大震災による津波のため、柳津〜気仙沼間が不通。JRはBRTによる仮復旧のあとBRT転換を提示。現在BRTとして運行。
津波被害によりBRTに〜大船渡線
東日本大震災による津波のため、気仙沼〜盛(大船渡市)間が不通。JRはBRTによる仮復旧のあとBRT転換を提示。現在BRTとして運行。
津波被害により不通〜山田線
東日本大震災による津波のため、釜石〜宮古間が不通。JRはBRT転換を提示。地元の反発のため、三陸鉄道へ移管する案が示されたが決定まで時間を要し、現在も不通のまま。
鉄道輸送に不向きとされ廃線〜三江線
2度に渡る洪水により不通となる。現在は全線運行中。利用客の減少に歯止めがかからず、また、水害による被災の可能性が増加したため、2018年4月に廃止することが決定。
JR北海道
維持費の節減が行き過ぎたため、度重なる事故により、国土交通省から改善命令を受ける。経営悪化のため、路線維持が不可能となり、沿線自治体に対し、路盤管理を持つか廃線かの提示。半分近くの路線が存亡の危機に立たされている。 |